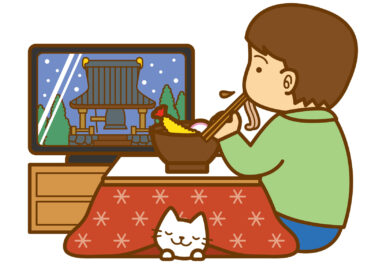9月くらいに古本屋で本を買いました。
私の住んでいるところはかなり田舎なので、古本屋も満足にないのですが、その日は期間限定で隣町のデパートで古本市が開催されていました。
以前にも書いたのですが、私は古本屋をふらりと歩きながら、好みの一冊を探す時間が好きです。
古本屋では時折、棚の隙間から思いがけない出会いが顔をのぞかせ、「新しい情報」や「話題の本」にはない、偶然のような出会いがあります。
けれどそうした出会いは、まるで偶然のようでいて、実はそのときの自分に必要な言葉や考え方だったりもします。
インターネットやSNSでは、自分の関心に沿った情報が次々と流れてきます。
便利で心地よい一方で、そうした環境の中にいると、世界が少しずつ狭くなっていくような気がするんです。
好きなものばかりを追いかけているうちに、気づけば他の価値観を受け入れる余白が小さくなっている──
だからこそ、ふらりと古本屋に足を向け「偶然の一冊」と出会うことは、私にとって一種の“バランスを取る行為”なのだと思います。
そこには、自分では探せない本、自分では選ばないはずの本との出会いがある──
そうした偶然の出会いが、自分の思考の輪郭をわずかに広げ、どこかに置き忘れていた感覚を静かに呼び覚ましてくれるのです。
ということで、今回出会った本はこちらです。「虹色ほたる」

表紙がキレイだったので購入しました。
初めはいわゆる「児童書」の類いだろうと、あんまり期待せずに読んでいたのですが、物語は定番でありつつもしっかりとしていて、情景描写も美しく、とても良かったです。
ちなみに2012年にはアニメ映画化もされているようで、そちらも観てみましたが、私は断然、小説版をおすすめします。
アニメ映画も風景描写は丁寧で美しいのですが、やはり人それぞれが思い描く「田舎の景色」や「懐かしい日本の空気」は違うものです。
小説の中で文字で読む物語は、読む人の心の中で一人ひとりのの想像が自由に息づき、自分だけの情景として立ち上がってくるのです。
この作品は、そうした“想像の余白”を楽しみながら、ゆっくりと時間をかけて味わうのが似合う物語です。
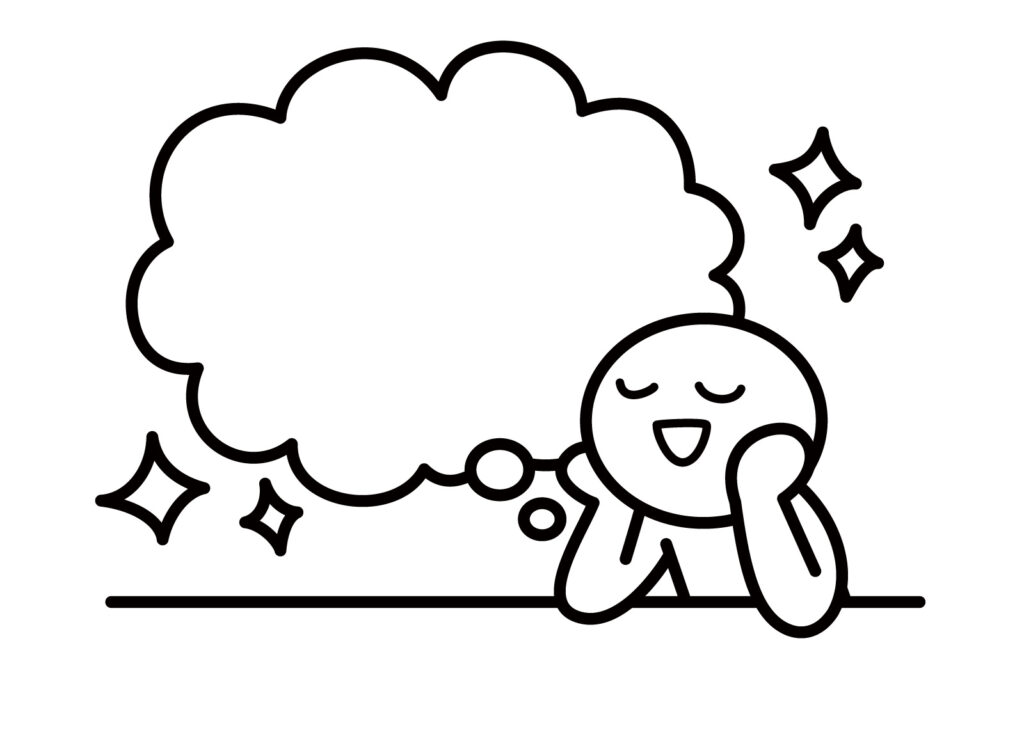
さて、話は変わり、この本のテーマは個人的には「出会い」「思い出」「古き良き日本」だと個人的には思います。
あらすじとしては、主人公の「ユウタ」少年が小6の夏休みに、30年前にダムの底へと沈んだはずの故郷の村に、不思議なタイムスリップをしてしまう。そこの村民の人と、今は失われてしまったかもしれない古き良き日本の田舎の夏を楽しむというものです。そして最後には、現代に戻るのですが、タイムスリップした時の記憶は消えてしまって…。
といった、まぁありがちと言えばありがちなのですが、個人的に好きな設定だったので楽しく読むことができました。
昔から、廃墟にはどこか心惹かれるものがあります。
実際に行く勇気はありませんが、そういった本やYouTubeをよく見ていました。
昭和の時代はダム建設のために村が沈んだというのはよく聞く話です。ダム建設が原因ではなくとも、インフラ維持や不自由な生活が原因で廃村になってしまった地域は割と多いです。
今はただ、沈黙と不気味な影を纏うだけの廃墟にも、かつては新築で、新しい生活への期待に胸を膨らませた住人がいて、日々の営みがあり、笑い声があり、その人生を見守りながら、やがて静かに訪れた別れがあったのだと思うのです。
そんな在りし日の物語を思うのが好きなのです。

ということで、この本は、そのような私の願望を疑似体験させてくれるのです。
そして、風景描写には「古き良き日本の田舎の夏」が丁寧に描かれています。
キーワードは「ほたる」「虫取り」「神社」「雷じじぃ」「おばあちゃん」
こんなところでしょうか。
私は正直、ほたるも虫取りも全く興味がなく、夏休みに神社で遊んだ経験もありません。
でも、なぜか「古き良き日本の田舎の夏」といえばそのような風景が思い浮かびます。
ちなみに、「雷じじぃ」という人は登場しません。今は絶滅危惧種となってしまった「近所の子供をきちんと叱る怖い他人のおじさん」のことをそう表現させていただきました。
一昔前に流行ったなろう系と呼ばれる「中世ヨーロッパ」的な世界観も正直好きですが(巷ではナーロッパと呼ばれているらしい)、こういった一昔前の日本を感じられる世界もいいですね。
もちろん、クラシック音楽やヨーロッパ絵画が好きな私からすれば、中世ヨーロッパも憧れます。
ですが、こういったステレオタイプな昔の日本の田舎的な風景にも憧れます。
まぁ、どちらの世界にタイムスリップしたとしても、現代の便利で豊かな日本で生まれ育った私には、長期間の滞在は無理そうですが…

誰しもが子供の頃に戻って、もう一度夏休みを経験したいなという思いがあると思います。
そういった願いと、昔の古き良き日本へタイムスリップしてみる、という私の2つの夢が疑似体験できました。そして、児童書らしくファンタジー要素もしっかりあり、全体的にキラキラしていてまるで汚いところがないです。
そして、元の世界に戻ったユウタの記憶はというと…。あまり書くとネタバレになってしまうので、内容については書くことができませんが、過去の記憶というのは、私くらい年齢を重ねてしまうと現実に起きたものなのかどうか、気づかぬうちに少しずつ色褪せていきます。
まるで古い写真のように、輪郭がぼやけ、当時の空気の匂いや人の声が少しずつ遠のいていく。
私くらい年齢を重ねてしまうと、時には「本当にそんなことがあったのだろうか」と、自分の記憶さえ疑わしく思えてくるのです。
記憶と夢の境界が、だんだんとグラデーションのように溶け合っていく感覚があります。
確かに体験したはずの場面が、夢の断片と重なり、いつの間にか曖昧な映像となって心の中に漂っている。

そうなると、「現実とは何か」という問いがふと頭をよぎります。
過去も未来も不確かで、確かなのは、今この瞬間、自分が息をして、何かを感じているという事実だけなのかもしれません。
けれど、だからこそ不安になるのです。
あのとき出会った人々、交わした言葉、確かに感じた温もり——それらは本当に存在したのだろうか。
思い出そうとすればするほど、記憶の中の光景がゆらぎ、まるで夢の中に手を伸ばしているような心もとなさを感じます。
そんなとき、私はアナログなものに救われます。
手書きの文字、擦り切れた写真、古い本の紙の匂い——そうした「物質として残る記憶」は、確かにそこにあった時間の証拠のように思えるのです。
デジタルデータの中の思い出は、いつでも取り出せるけれど、どこか現実味が薄い。
けれど、アナログの記憶は、時間と共に劣化しながらも、確かな「存在の重み」を持っている。
だから私は、失われていく記憶を少しでもこの手の中に留めておきたくて、古い写真を見返したり、当時描いた絵を眺めたり、もらったプレゼントを大切に保管するのかもしれません。
それは、過去を確認するというよりも、記憶と現実のあわいをそっとつなぐ、いまの私にとっての“生”の形なのかもしれません。
そういったことを再確認させてくれるおすすめの一冊です。