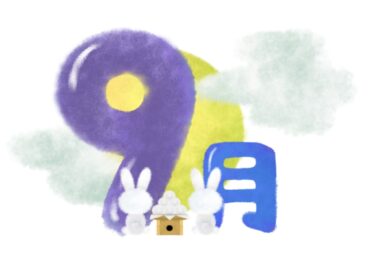どうやら、海外のNetflix(ネットフリックス)でジブリ作品の名作「火垂るの墓」が公開され、話題となっている見たいです。
「火垂るの墓」といえば、第二次世界大戦の日本を舞台にした作品。
原作者の「野坂昭如」氏が自身の戦争体験を元に描いた作品なので、妙な生々しさがあります。
それゆえ、いくらアニメといえどもグロテスクな表現もあり、人が多数死んでいく内容なので、かなり覚悟を持って視聴しなければ耐えられないです。
それでも、第二次世界大戦の敗戦国である日本に住むものとしては、必ず見て欲しい内容だと思っています。
私も最後に見たのは小さい頃だったので、今回改めて見直してみましたが、正直胸が苦しくなってノンストップでは見れず、ところどころ飛ばしながら見ました…。

火垂るの墓の大まかなあらすじ
大まかなあらすじは以下の通りです。
※【注意】
(若干のネタバレを含んでいるので、ネタバレしたくない人は飛ばしてください。しかし、この作品に限っては、前知識なしだとかなり衝撃が大きすぎるので、あらかじめ一通りストーリーを把握してから視聴した方がショックが少なくて済むかも知れないです)
主人公は清太(せいた)という名の14歳。やさしく、妹思いの性格。
物語は1945年9月21日、その日に清太が亡くなり、幽霊となった清太が自分の亡骸を見つめているところから始まるという、衝撃的な始まり方をします。
亡くなった清太を忌み嫌うように、冷酷に通行人が清太を避けて歩きます。
そしてホタルが舞う中、同じく幽霊となった節子を清太が手をつなぎ歩いていくというシーンでオープニングを迎えます。
そのシーンの後は彼らの住む神戸市が空襲に遭い、清太の家を含めあたりは焼け野原に。

なんとか清太と節子は逃げ切れましたが、先に避難先に向かっていた母は大やけどを負い、帰らぬ人になってしまいます。
帰る家と母を亡くした清太たちは、「もしものことがあったら」と清田の母があらかじめお願いしていた叔母の家にお世話になることになります。
ですが、食糧難のこの時代です。
はじめのうちは清太の母が残してくれた食糧を持ち込んだこともあり、二人に優しく接する叔母ではありましたが、自分の家族が満足に食べるだけの食糧を確保することも難しくなる中、叔母は二人に対して不満を持つようになり、露骨な差別したり、嫌味を言ったりするようになります。
その生活に嫌気が差した清太は、叔母の家を出て川近くの防空壕で節子と2人だけの生活を始めます。
初めのうちは邪魔者もいなく、自由気ままな生活ができて、わずかな時間でしたが振り返ってみると、清太と節子の幸せの頂点だったような時間でした。二人の幸福な生活を照らすようなホタルの美しさが印象的です。

しかし、蓄えも徐々に亡くなり、地域とのコミュニティもない清太たちは配給ももらうことができず、近くの畑から盗んできた農作物でなんとか命をつなぐ生活。
もちろん、盗みが成功する日ばかりではありません。泥棒がバレてしまい、タコ殴りにされたことも…。
そういう極めて厳しい生活が続く中、ついに幼い節子が栄養失調で体調を崩してしまいます。
しかし、いつかは日本が戦争に勝利し、父が迎えに来てくれることを信じ、日々の困難に耐える二人。
ですが、その前に節子の命の灯火が消えかかっていました。
病院に連れていくも、「滋養を付けるしかない」と治療はおろか、薬さえもらえない始末。
おそらく、医薬品も不足していたであろうし、戦争孤児であった二人はそんなに良い扱いを受けなかったのではと推察します。
でもとにかく、食糧にありつけなければ節子は亡くなってしまいます。
清太は、なけなしの貯金を全部おろし、節子に食べたいものを食べさせることに。
しかし、節子は清太に「いかんといて」と、待っている間一人寂しく待つのが嫌な様子。
でも、このままでは節子は…。
「いつでも節子のそばにおる」と約束し、銀行でお金を下ろす清太。
その途中、日本国の敗戦と父の所属する連合艦隊が壊滅した、つまり父の死を知ります。
「日本の勝利と父が帰ってきて一緒に暮らす」という唯一の希望が途絶え、絶望する清太。
妹の節子のためになんとか食糧を集め、節子の元に戻るが、時すでに遅し。
節子は亡くなってしまいました。
というこれ以上悲しいストーリーが存在するのかというくらい、残酷で悲しいストーリーとなっています。

火垂るの墓は、実は幽霊になった清太が客観的に自分の人生を回想している映画!?
このシーンは先ほど述べたように、清太の幽霊と思わしき人物が自分の亡骸を見つめるシーンから入ります。しかし、その見つめている清太はまだ息をしています。つまり、死んでいない。
ではなぜ自分の亡骸を見つめているのかというと、おそらく、この物語は幽霊となった清太の回想なのではと思いました。だから、完全に亡くなった後の清太は物語には登場しません。そして、幽霊になった清太が、現代の神戸と思われるビルが並ぶ夜景を節子と眺めるシーンで物語が終わります。
ここら辺の解釈は、岡田斗司夫さんが詳しく解説してくれています。※作者の解説ではないので、あくまで仮説の中の一説であることに留意してください。
子供の頃に見るのと大人になってから見るのではまた印象の違う作品
私はこの作品を子供の頃にもみていましたが、大人になった今また見てみると違う見え方もしてきて、大変興味深いなと。
母が亡くなった後、清太たちは疎開先のおばさんの家にお世話になりますが、徐々に清太に対して差別をしたり、嫌味を言ったりして、そのことに嫌気が差して清太は自分達だけで暮らすことを選択します。
子供の頃意地悪なように映ったおばさんも戦時下という極限状態でいっぱいいっぱいだった説
子供の頃、このシーンを見て
「なんてひどいおばさんなんだ!おばさんが実質清太を追い出し、節子を殺したんだ!」
と思いましたが、大人になった今、時代背景などを考えると、いくら清太がお米や梅干しを持ち込んだとしても、おばさんの家も自分達家族が食べていくだけで精一杯なはず。
事実、清太が食べ物を持ち込んだ数日の間はおばさんの機嫌もよかったですが、それが次第になくなるにつれ、徐々に機嫌が悪くなっていきます。
清太が働いたり、勉強もしてないのもおばさんにいい印象を与えなかったと思います。
大人の私なら、戦時下ということもあり食料を確保できる見込みもないので、多少おばさんの意地悪を我慢しても踏みとどまると思います。
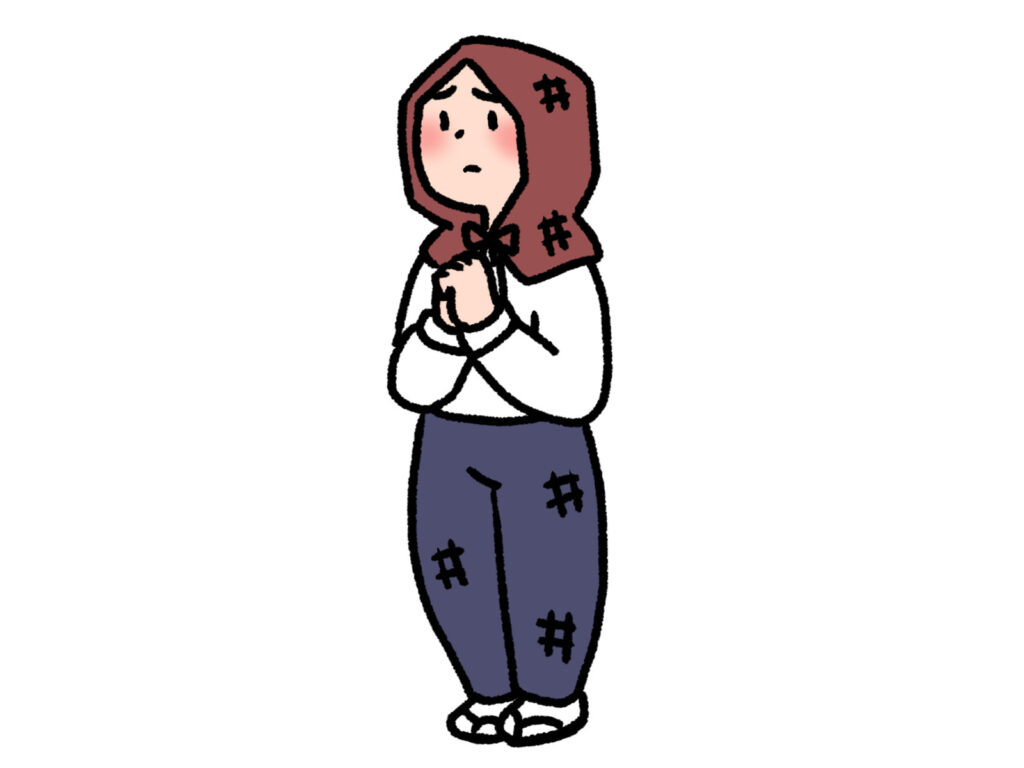
清太が悪いというけど、まだ14歳の少年だということを忘れてはいけない
ただ、忘れてはいけないのは清太はまだ14歳だったということ。
14歳というのもまた絶妙な年齢設定で、私の14歳の頃を振り返ってみると、大人になりかけで自分ができることも増えて身長も大人並みくらいに大きくなり、根拠のない自信というか、謎の万能感に溢れていました。
ましてや清太の父は海軍大佐。母が亡くなる前までは裕福な家の息子だったのです。
現に、作中の回想で綺麗な着物を見にまとい、家族写真を撮影するシーンがあります。
現実的に考えて裕福な家庭に育ったの14歳の男の子が、いきなり母を亡くし、親戚のおばさんに邪険に扱われたら耐えられないのも無理はないかなと。
ましてや、思春期特有の謎の万能感も相まって、それでおばさんの家を出てもなんとかなるという考えに至ったのではないでしょうか。

バブル期は清太擁護派が多数。今は清太批判が多数。
ですが、火垂るの墓を見た人の感想を覗いてみると、清太に対する批判が多く感じました。
「清太があそこで我慢していれば節子は助かった」と。
しかし調べてみると、この映画放映当時の1988年は、清太擁護派が圧倒的に多かったようです。
1988年の日本といえば、バブルの絶頂。日本が一番裕福だった時代なのです。
その後、バブルが崩壊し、30年間日本は経済が低迷します。
清太を批判する人が増えたということは、戦時中と同じく、現代日本に余裕のない人が増えたからではないでしょうか。
火垂るの墓の監督である、高畑監督の当時のインタビューにこうあります。
当時は非常に抑圧的な、社会生活の中でも最低最悪の『全体主義』が是とされた時代。清太はそんな全体主義の時代に抗い、節子と2人きりの『純粋な家族』を築こうとするが、そんなことが可能か、可能でないから清太は節子を死なせてしまう。しかし私たちにそれを批判できるでしょうか。我々現代人が心情的に清太に共感しやすいのは時代が逆転したせいなんです。いつかまた時代が再逆転したら、あの未亡人(親戚の叔母さん)以上に清太を糾弾する意見が大勢を占める時代が来るかもしれず、ぼくはおそろしい気がします。
引用:高畑勲『アニメージュ1988年5月号』徳間書店「88年の清太へ!」

時代が違えば清太もおばさんも普通の人
でも、清太も、おばさんのことも批判するのは本質的とはいえません。
なぜそのような状況になってしまったのか。それほど戦時中の環境が最悪だったのでしょう。
言ってしまえば時代が悪い、その一言に尽きます。
終盤でとても印象に残ったシーンがありました。
節子が亡くなった後の終盤で、終戦後疎開先から自分宅へ戻ってきたと思われる少女が、甲高い笑い声を上げながら走ってきて家に戻り、蓄音機で音楽をかけるシーンがありました。
また、冒頭のシーンで清太が駅舎の中で死を待つ状況の中、白米のおにぎりを見知らぬ人が置いていくシーン。
清太と節子の家は空襲で焼けてしまい、自身も戦火を生き残れなかったです。しかし、疎開先から戻ってきた少女たちの家は残っており、おそらく戦後の豊かな日本を謳歌するのです。
そして、戦時中はいくら清太がお腹をすかせてもびた一文とも分けてもらえなかったのに、戦後ではそれも見知らぬ人からおにぎりをもらえるのです。
基本的に「人の人生は不平等なんだよ」と言われている気がしてなりません。

清太・節子と疎開先から戻ってきた少女たち。そして戦時下を生き抜いた人たちと我々戦後生まれの日本人。
現代に生まれていれば、清太もおばさんも普通の人だったに違いありません。ただ、時代が悪かった。
わたしたちの今の生活は先人の努力・犠牲があったから成り立っていることを忘れてはいけないと強く思いました。そして私たちも次の世代のために頑張らないとと。
清太と自分が重なるところがありました。
コミュ障の私はコミュ障の清太に親近感が湧いた
運よく現代に生まれてきた私ですが、果たして、戦時中に生まれていたら生き残れていたのでしょうか。
コミュ障の私がうまく世渡りしていけるイメージが湧きません…。
ですが、この作品を見返して、最後に頼れるのは人間関係なのだなと強く思いました。
今の平和なこの世の中は、お金さえあればものが何でも手に入る時代。でも、作中にもあるように、戦時中はお金があってもものが手に入りませんでした。
人と仲良くし、世渡りがうまくないと生きていけない時代でした。
なので、コミュ力を上げることは大事なのだなと痛感しました。
そして、他人を思いやること、感謝の気持ちを持つことは大事。これからもそうありたいと思いました。
地域のコミュニティが薄れ、人間関係が希薄になっていった現代日本。
幽霊となった清太と節子は高層ビルを眺めながら現代の日本をどう思っているのでしょうか。